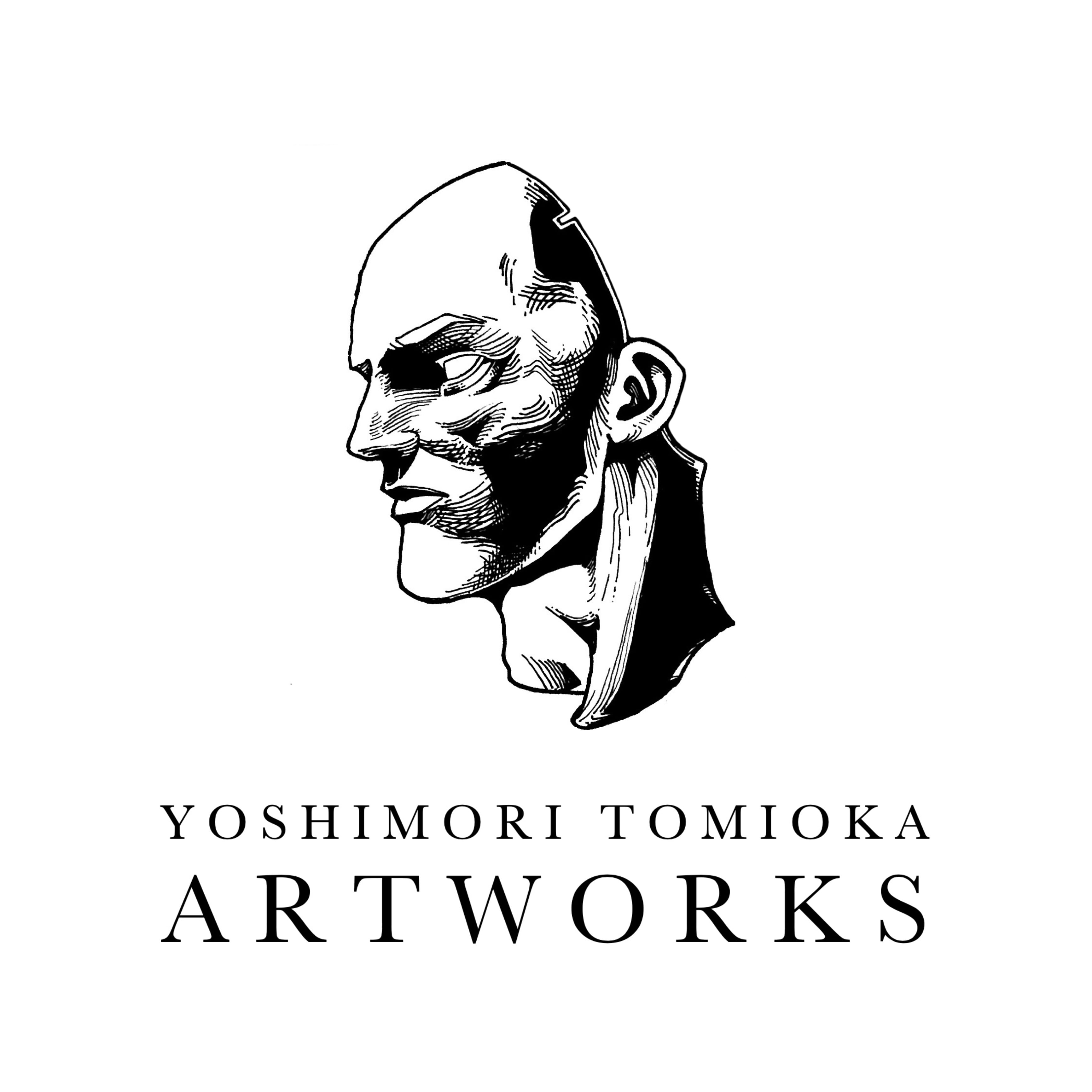Profile
Artist(画家 写真家)。東京在住。
絵画制作における主題は〈 人間と機械 〉。
ミリペン・金色ペン・金色絵具を用い、人格や感情、社会と機械の相互作用を探究する。
写真制作における主題は〈 連続性 〉。
KODAK ULTRA F9・iPhone 12 Pro Maxを用い、物質や時空、生命と都市の連続性を探究する。
Artist Statement(絵画)
〈 人間と機械 〉を主題に制作。
人格や感情、社会と機械の相互作用を探究する。
Key Phrase
二年ごとに制作の指針となるキーフレーズを設定。
01. 2020–2021:〈 人間に擬態する機械人間 〉
定型的に発達する人間と、非定型的に発達する人間との関係を考察。
・解説
現代社会における神経学的少数派は、神経学的多数派によって形成された支配的文化の中で周縁化され、十分に社会適応できない状況に置かれている。
そのため、多くの少数派は、自己の特性を覆い隠し、多数派の行動様式や言語、感情表現を模倣することで、社会的ハンディキャップの克服を試みる。このような擬態的行動による適応は、当人の精神的負担を著しく増大させ、二次的な障害を引き起こすリスクを高める。
しかし、本来このような困難の原因は、個人の側にではなく、特定の神経特性を基準として構築された社会構造の側にある。神経の多様性は人格の本質に関わるものであるため、それを一方的に抑圧しなければ生きられない社会は、明確に差別的であり、非人道的な構造を孕んでいる。
この、非定型的に発達した人間が環境に適応しようとする現象は、外的要請に応じて自己を最適化するアルゴリズム的な過程と類似しており、機械のような構造を帯びる。
そこで、このような擬態的行動を〈人間に擬態する機械人間〉と捉えることで、神経多様性をめぐる現代社会の不均衡を可視化し、同時に「人間性とは何か」という根源的な問いを、制作を通して探究する。
02. 2022–2023:〈 失われる人間性 〉
社会構造への過剰適応を示す〈 機械化する人間 〉と、科学技術の進歩によって〈 人間化する機械 〉との関係を考察。
・解説
大規模定住社会から始まった社会構造の複雑化は、産業革命以降、加速度的に進行し、人間はますます合理化・規定化・計算可能化を志向するようになった。それは、複雑化した社会を生き抜くための、生存戦略としての学習的適応である。
しかし、人間と機械の特性は明確に異なる。それは、端的に言えば、人間の特性は偶発性にあり、機械の特性は計画性にある、ということである。
この対比において、社会構造への過剰適応によって人間性を失いゆく人間を〈機械化する人間〉と呼び、科学技術の進歩によって人間的特性を獲得しようとする機械を〈人間化する機械〉と呼ぶ。
このような状況の中で、〈失われる人間性〉の構造を可視化し、〈機械化する人間〉と〈人間化する機械〉との関係を、制作を通して探究する。
03. 2024–2025:〈 人間の流体性 〉
人間の流動的な側面と、再構築される記憶や人格、自己意識について考察。
・解説
生命は、静的なシステムではなく、情報の交換によって秩序を維持する動的なシステムである。代謝活動により個体を構成する分子は一定の周期で置換されるが、全体の構造は安定して保たれる。したがって、生命とは固定的・機械的な構造として理解するものではなく、情報の流れの中で持続する流動的な秩序として理解すべきものである。
この枠組みは、精神的な現象にも適用できる。例えば、記憶は固定的に保存されるものではなく、想起のたびに神経回路が編成される再構築的なプロセスである。また、人格は不変的な心理的特性ではなく、社会的文脈に応じて変動する可変的な構造である。このように、記憶や人格などの精神的現象も、情報の流れの中で再構築される動的な現象である。
この観点からすれば、自己意識とは恒常的な実体ではなく、物理的な相互作用によって一時的に形成される情報構造であると理解できる。〈人間の流体性〉とは、自己意識を情報過程として捉えた際に観察される、動的な生成プロセスのことであり、この構造についての探求と可視化が、本期の制作目的である。
04. 2026–2027:〈 人類代の終り 〉
水平化する人間の価値、インスタントな生命観、分散する人類種について考察。
・解説
人間の認知や情動は、神経信号の電気的振動や化学的伝達の相互作用に基づいて形成される。外界の刺激は受容体を介して電気信号へと変換され、中枢神経で処理される。このとき、神経系のリズムは、音楽・形態・言語などの外的刺激に内在する周期構造と共振し、認知判断や感情反応の基盤を形成する。この点において、人間の精神的活動は、外界の構造的なリズムと神経系のリズムの共振現象として理解できる。
また、現代社会においては、社会的な情報ネットワークの発展により、個人の神経リズムと社会的な情報ネットワークとの間にも構造的な相似性が生じている。社会的情報ネットワークにおける情報の相互作用は、神経回路における信号伝達と同様に、反復や同期、拡散といったパターンを示す。したがって、人間社会全体を、一種のマクロ的な神経系として捉えることが可能である。
この構造的な類比を拡張すると、人間・社会・宇宙を貫く情報の流動性は、フラクタル的な階層構造をもつ自己相似的共振体系として理解できる。このような視点において、「人間的なるもの」は、もはや有機的な身体に限定されず、情報の振動パターンとして存在する。私は、このような存在形態の転換期を〈人類代の終り〉と呼ぶ。それは、人類の消滅を意味するのではなく、人間中心主義的な枠組みの終焉を意味する。
本期の制作では、ミリペンによる描線の累積や律動的な反復を通して、この「波動的な存在構造」を視覚化する。そして、〈人類代の終り〉における新しい人間像──分散的かつ共振的存在としての人間──を提示する。
画材と技法
本制作に使用される画材は、ミリペン・金色ペン・金色絵具である。また、本制作には、表現技法として描線によるモアレパターンが多用される。これらは単に思想・概念を可視化するための補助的な手段ではない。描線の不可逆性、誤差の累積、観測条件依存的な知覚、階層的干渉による秩序の双発は、制作過程および鑑賞過程の双方において、自己・社会・価値といった情報の秩序が動的に生成・維持・更新される過程を、物質的現象として提示する。
01. 不可逆的痕跡としての描線生成
ミリペンは、一定の線幅とインク供給を前提とした描画装置であり、描線は一度生成されると消去・修正が不可能である。
この不可逆性は、単なる比喩的象徴ではなく、制作過程そのものに強い制約条件を与える物理的特性である。本制作において、ミリペンは「表現のための道具」ではなく、不可逆的痕跡生成を強制する環境条件として機能する。
描線は、制作者の意図・運動・判断が、後戻り不可能な形で画面に固定される点において、予測誤差最小化を行う生体システムが、過去の行為履歴を内部状態として累積していく過程と構造的に対応する。
このときに重要なことは、描線の不可逆性が、完成像の決定ではなく、局所的な行為選択の連鎖を拘束する点である。制作者は、すでに描かれた線を前提条件として次の線を選択せざるを得ず、描画過程は常に、既存の生成モデル(画面上の線の分布)と新たな行為との間の予測誤差を調整する過程となる。
その結果として、画面に現れる秩序は、事前に完全に計画された構図ではなく、不可逆的制約下で局所的最適化が反復された結果として出現する準安定状態である。この点において、ミリペンによる描画は、自由エネルギー最小化系が環境制約の中で一時的な安定点を探索する過程を、物質的に実装した実験系なのである。
02. 予測誤差顕在化としての描線の揺らぎ
ミリペンは、均質で計算可能な線を安定して生成するよう設計された道具である。しかし、その運用は最終的に人間の身体運動に依存するため、微細な震え、圧力変動、速度変化といった誤差を完全に排除することはできない。
本制作では、この揺らぎを「排除すべきノイズ」としてではなく、予測誤差が物質的に顕在化した痕跡として積極的に保持する。描線の揺らぎは、制作者の内部予測(意図された線)と、実際に生成された線との差異として現れ、その差異は次の行為選択にフィードバックされる。
このときに重要なことは、この誤差が即座に修正・消去されない点である。誤差は画面上に残存し、新たな制約条件として以後の描画過程に組み込まれる。したがって、描画は「誤差を消す行為」ではなく、誤差を含んだ生成モデルを更新し続ける過程となる。
このプロセスは、神経系が感覚入力と予測との乖離を完全に解消するのではなく、一定の誤差を内包したまま安定化する様式と構造的に対応している。描線の揺らぎは、自己が常に完全な予測に到達することなく、誤差を抱えたまま秩序を維持する存在であることを、物質的なレベルで示しているのである。
03. 金色の持つ観測条件依存性と聖性
金色の描画材は、顔料に含まれる金属粒子によって、入射光と観測角度に応じて反射特性が変化する。このため、同一の画面であっても知覚される色味や輝度が不安定に変動する。
この特性は、金色を単なる象徴的色彩としてではなく、観測条件依存的に振る舞う情報構造として機能させる。金色による描線や面は、視点移動によって鑑賞者の予測を裏切り、知覚的誤差を反復的に生起させる。この知覚的な不確実性は鑑賞者にとって、画面が固定的な像として把握されることを妨げ、自己と作品との関係を動的なものへと移行させる。すなわち、鑑賞行為そのものが、予測と誤差修正の連続的過程として組み替えられる。
このとき、作品は完結した像ではなく、鑑賞者との相互作用の中で一時的に安定する情報秩序として成立する。したがって、作品の完成とは物理的な終点ではなく、鑑賞という行為のたびに異なる準安定状態として生成される出来事である。
宗教美術において古来より金色が担ってきた「聖性」とは、単なる超越的実体の表象ではなく、本来的には、人間の知覚と理解を超える構造の存在を示唆する装置であった。本制作では、この機能を再解釈し、金色を、階層を異にする情報秩序が知覚レベルに介入する現象として位置づける。
04. 高次秩序としてのモアレパターン
モアレとは、複数の周期構造が重ね合わされることで、個々の構造には存在しなかった新たな周期パターンが知覚される現象である。本制作では、グリッドや反復描線といった規則的構造を意図的に重ねることで、この現象を二次元平面上に生成する。
ここで生成されるモアレは、単なる視覚的効果ではなく、複数の生成モデルが同時に作用した際に生じる高次秩序の視覚的副産物として位置づけられる。各描線やグリッドは、それぞれが局所的に最適化された秩序であるが、それらが重なり合うことで、制作者が事前に設計していなかったパターンが出現する。
この出現過程は、個体内の神経階層、社会的情報ネットワーク、さらには宇宙論的スケールに至るまで観察される、階層間干渉による秩序創発と構造的に対応している。本制作におけるモアレパターンは、下位秩序の単純な総和では説明できない秩序が、相互作用の結果として立ち上がることを、平面上で直接的に示しているのである。
写真制作のArtist Statementについては、noteを参照してください。
Biography
1999
・神奈川県生まれ
2020
・横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 絵画コース 中途退学
・AAA Gallery「スチームパンク〜まわる歯車〜展」
・MIRAIE Gallery「第11回 感性の息吹展」
・東京ビッグサイト「Design Festa vol.52」巨大ライブペイント
2021
・AAA Gallery「ペン画の世界展〜第Ⅷ画〜」
・東京ビッグサイト「Design Festa vol.53」ライブペイント
・Boji Gallery「Decorate the cover展」
・Dance Studio WAAAPS「FUDE ROCK」準優勝
・東京ビッグサイト「Design Festa vol.54」ライブペイント
2022
・Boji Gallery「みんなの年賀状展」
・Boji Gallery「CHANGE わたしたちの近未来展」visual
・渋谷 UNDER DEER Lounge「FUDE ROCK 2」2on2優勝
・Boji Gallery「Recommend the 家電展」
・Design Festa Gallery「Cells-illustration-vol.32」
・下北線路街 空き地 「笑う門出に春来たるッ」
・東京ビッグサイト「Design Festa vol.55」ボジキャラバン
・Boji Gallery「TWIN展」
・バトゥール東京 起業記念パーティ ライブペイント
・渋谷 Contact「FUDE ROCK 3」敗者展 1位
・コミュニティスペース&ギャラリー山本屋又右衛門「アゲアゲ☆ライブペインターズ vol.2」
・Boji Gallery「早く人間になりたい!」個展
・Gallery 螺旋「最愛なるご主人様」
・Boji Gallery「The shade of black light arts show」
・東京ビッグサイト「Design Festa vol.56」ライブペイント
・登戸・遊園ミライノバ「のぼりと商店」
・東中野ALT_SPEAKER「笑う門出に冬来たるッ」
・Gallery ARTIST GUILD「才能が弾ける音がした。」
2023
・代々木公園 野外ステージ「FUDE ROCK 4 東京予選」敗者展 3位
・Design Festa Gallery「冨岡理森×ミケタ 2人展 “て”」
・ゆうゆう高円寺南館「余寒を蹴飛ばせ!絵描きバトル」主催
・Design Festa Gallery「転んで光った」MINI個展
・Design Festa Gallery「冨岡理森×ミケタ 2人展 “human-oid”」
・Design Festa Gallery「冨岡理森×幹夫800 MINI 2人展 “ひかり”」
・東京ビッグサイト「Design Festa vol.58」物販
・STORIES TOKYO「CINEMA STORIES TOKYO vol.1」
・STORIES TOKYO「CINEMA STORIES TOKYO vol.2」
2024
・Design Festa Gallery「NARABETEMITA」コラボゲスト
・Design Festa Gallery「ただ、そっとしておいて」
・Design Festa Gallery「肯定の過剰摂取」
・Design Festa Gallery「律動する色彩」
・Design Festa Gallery「爆発的膨張」
・Design Festa Gallery「冨岡理森×幹夫800 2人展 “常夜灯”」
・Design Festa Gallery「存在の濃淡」個展
・Design Festa Gallery「溶けて光って」個展
・STUDIO SOUKO 450「Sweet spot party」
・流山おおたかの森S・C「筆ロックチャレンジinおおたかの森」ライブペイント
・Design Festa Gallery「冨岡理森×あんちゃーりー 2人展 “あやふや好奇心”」
2025
・Design Festa Gallery「人間機械論」
・Design Festa Gallery「ミケタキカク vol.8 黒×? 第4弾」
・Design Festa Gallery「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」
・Design Festa Gallery「人間と機械の関係について」